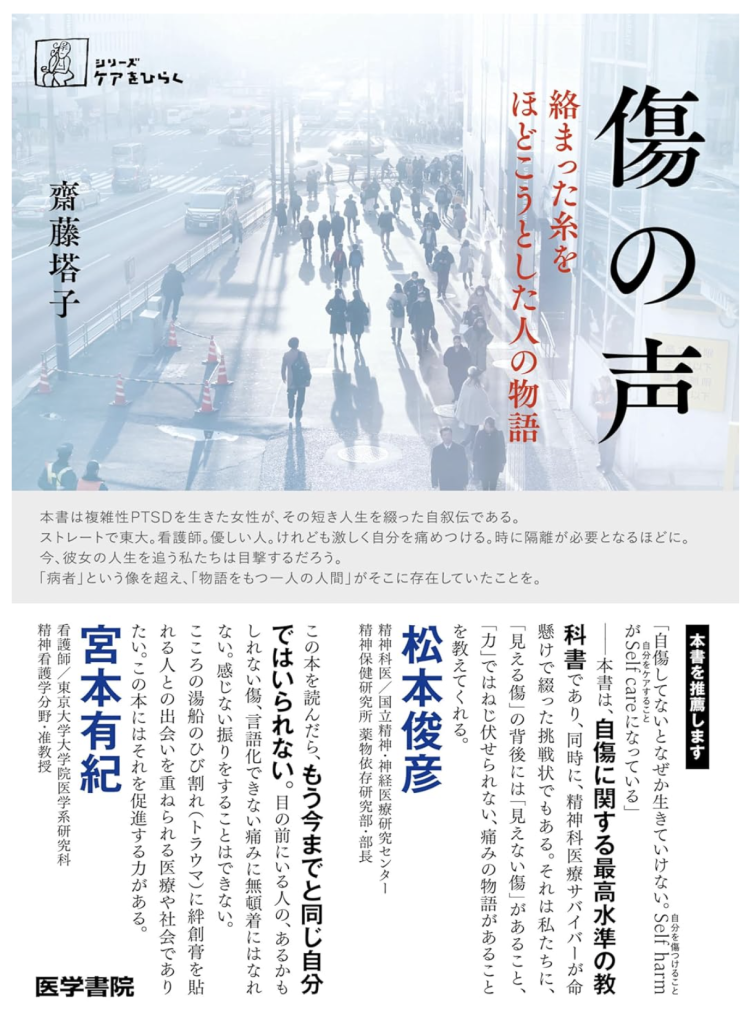
ドイツにてシングルママ子育てを卒業したSunnyです。
最近、医療関係の仕事をしている友人と、「お酒やタバコをやめたいのに、やめられない人」の話から派生して、人の心に関する深いテーマになりました。その流れで彼女が持っていた本、『傷の声 ― 絡まった糸をほどこうとした人の物語』(齋藤塔子 著)を借りる流れとなったのですが、引き込まれて2日で一気に読了しました。
著者は、ストレートで東大に合格し、看護師。しかし時に隔離が必要になるほどの自傷行為をしてしまうほど、心に傷がある。
ご存知ない方のためにかいつまんで内容を説明すると、複雑性PTSD(C-PTSD)を抱えた著者が、自らの心の傷と向き合いながら生きてきた記録を綴った、ノンフィクション作品です。当事者にとっては、心の傷が深すぎるがため自傷をするのですが、その行為がセルフヒーリングになるということを、私はこの本で初めて知りました。
つまり、あまりにも辛い心の痛みから一時的にも解放されるために、意識を体の痛みに持っていく、というのが自傷であることを知りました。
複雑性PTSDとは、長期間・反復的なトラウマ体験によって生じる心の障害で、通常のPTSD(心的外傷後ストレス障害)よりも症状が深く、広範囲にわたるそうです。
- 幼少期の虐待(身体的、性的、心理的)
- ネグレクト(育児放棄)
- DV(家庭内暴力)
- 拷問、誘拐、性的人身売買、監禁など
と、最初からなかなかに重たい内容ですので、元気な方のみこの先を読み進めてくださいね。
ちなみに私はこういった人の心に関するテーマに興味があるので、とても勉強になりました。
家庭内が嵐の中で育つ恐怖
日本とドイツで19年間子育てをしてきた中で、幼少期や思春期の家庭環境が悪くて、子供に問題が出るケースを1人の子を持つママとして、悲しいかな目撃することが何度かありました。その度にとても心が痛み、ママさんパパさん達の心の闇みたいなものを狭間見ることもありました。
かくいう私は、家庭崩壊の中で育ちました。
両親は別居するまでほぼ毎日喧嘩をしていたし、両親の喧嘩が勃発する夜は、毎回「この世の終わり」のように感じていました。
大人にとっては、些細な喧嘩かもしれません。しかし、小さな子供、いや小学生、中学生、高校生でも、両親の喧嘩を目の当たりにするのは、恐怖以外の何ものでもありません。これを書きながら、フラッシュバックのように様々な思い出が蘇ってきます。
例えば、家族で行った数少ない旅行に、車でディズニーランドへ行った思い出があるのですが、道中で両親が怒鳴り合い、ヒステリーな叫び合いの喧嘩をして、居心地が悪過ぎてその感情から逃げるように、太ももをつねっていたことを思い出しました。なので私の中では家族と行ったディズニーランドが楽しかった、という思い出はありません。夢の国のはずなのに。
おぼろげながら、楽しかった時の思い出もあるのですが、一貫して脳裏に焼き付いているのは、不幸せそうな母の姿です。
この本の著者は、共依存関係にあったであろうご両親の度重なる喧嘩と、父親の怒号が頻繁に起こっていた家庭で育ち、とても小さい頃から不眠に悩まされていたそうです。高校生の頃には睡眠薬他何種類かの薬を服用していたそうです。
思春期には、母親から父親の悪口を延々と毎日聞かされ、挙げ句の果てにはその憎き父親と自分が似ていると、母親から言われ続けていたそうです。
そのため、自己肯定感など芽生えることもなく、心の傷は深まり続けたようです。
私の子育て初期
話が前後しますが、私は20代の頃に若くして母親になったのですが、その際、「子育ては自分の幼少期の追体験になる」と感じたことが多々ありました。
当時、娘が小さい頃のイヤイヤ期に、すでに国際別居をしていてひとり親だったのですが、夜泣きで毎晩3回は起こされる日々が3年くらい続いていたのもあり、心底疲れていました。そのため、心に余裕がなかったのもありイライラしていることが多く、小さなことでプチンと切れることがありました。その時に、自分が幼少期の時に見た、鬼の形相でヒステリックに怒る母を自分の中に発見し、心底自己嫌悪に陥っていた時期がありました。
そんな悩みを周りの一回りくらい年の離れたママ友さんに相談したことがあるのですが、感情の揺らぎを「若さ」のせいにされることもありました。その度に、なんとも言えない無理解に苛まれ、ママ友さんに相談するより、怒った日は娘をハグして謝り、娘と対話するようになりました。この時、小さな娘の中に傷を負った幼少期の自分を重ね、あの時母にしてもらいたかったことを自分の娘にするようになりました。
そのうち、自分の両親も両親から充分温かい愛情をもらっていなかったのではないか、と思うようになりました。
そのため20代は子育てを通して、待ったなしで毎日降りかかってくる感情の渦と向き合い、理不尽に怒鳴った後には必ず娘に懺悔をするようになりました。この時から私は娘と対等に話をしてきたので、達観したような考えを持つ子供になってしまった感が否めません。
ですが、当時の感情の渦と向き合うには、自分が自分と真正面から対峙するしか解決方法がなかったと感じていたため、「子供だからこれは言わないでおこう」とか「子供だからファンタジー(嘘)を入れ込もう」とか考える余裕などありませんでした。なぜなら、どうしても負のループは自分の代で終わりにしたかったのです。
その後、家族の負のループを紐解くべく、父方の親戚に何度か父の幼少期の話を聞くことができ、父のことを理解できるまでになりました。
そして、大分後にはなりますが、母方の親戚にも母が育った家庭環境を詳しく聞く機会を設け、母のことも理解できるようになりました。
また、ドイツ移住してからは周りに子育てを助けてくれる大人の手が劇的に増えたので、日本でのシングルママでの子育てのストレスは大分軽減されたのもあり、自分の心を鎮められるようになりました。
苛立ち、呪縛、そして選択
この「傷の声」を読み進めていくうちに、著者の父親が母親の行動制限をしていた場面では、2000年代だというのに、家父長制が色濃く出ていた著者の家庭に、まるで私の母が育った環境のようだなと思いました。
そして再確認しました。
早くに他界していた私の母も、恐らくずっとずっと亡くなる時まで、心に傷を負っていたであろう、と。
私は、父と離婚して欲しかったのに離婚できなかった母に対して苛立ちを感じていた時期があったのですが、この本の著者もまた「子どもたちのために離婚して欲しかった」と綴っています。離婚してくれていたら、さぞかし平和な思春期を過ごせただろうに、と。
著者の家庭背景には、「経済的に離婚できない」という理由があったようですが、モラハラやDV家庭に長いこと慣れてしまっていると、自己肯定感や行動力が著しく損なわれるので、多角的に物事を考えられなくなります。自分に自信がないので、全ては自分のせいだと考えるようになるし、誰かに相談するとか、相談できても間違った1人だけになり、セカンド、サードオピニオンを聞くという視点や勇気が持てません。
私の両親の場合は、「離婚」そのものが「悪」だと捉える世代だったので、そもそも選択肢になかったように感じます。
結婚したなら不幸であろうが何が何でも一生を添い遂げる、という呪縛に囚われていたのです。
そうして、家族全員に心の影を落とすことも知らずに。
私はそんな両親を見ていたので、自分が結婚してから、夫婦として家族として元夫とチームワークが機能しなくなった頃(結婚2年目でしたが)、話し合いを重ねはしたものの、早々に離婚を選択しました。
今思えば、結婚して、あまり長いこと体験として持っていない”温かい家庭”をゼロから築くことと、幼少期のトラウマを抱えながら同時に子供を育てるという、2つの重責に耐えきれなかったのだと思います。
兄弟間の認識の違い
著者は自身が深い複雑性PTSDを抱えていながらも、お母さんとお兄さんに当時の話を聞きに行きます。
お兄さんとの認識の違いに違和感を感じたこと、お母さんに聞きたいことが聞けなかったこと、リアルに感情を細やかに描写しています。
私の場合、自分の子育てで日々痛烈に感じていた幼少期の辛い思い出について、兄達と昔サクッと話をしたことがありました。
そして、著者と同じように兄と話をしていた時に、見えていた景色が全く違かった部分があり愕然としたのを思い出しました。
この時、それまで自分と娘だけの日常になかった、男性の理論的考え方がバズーカ砲のように投げ込まれたようで、衝撃だったのを覚えています。また、これだけ自分が一生懸命に負のループを自分の代で断ち切るために、真っ向から向き合い続けていわば戦っている中で、幼少期の彼らは私よりも幸せな思い出を持っていたのか、と嫉妬感情も湧きました。
最後に
著者の体験を読み進めることは、同じ経験がある方にとっては特にとても辛いものです。フラッシュバックもあるだろうし、感情が揺さぶられると思います。それでも、著者は自分が沈み込んだ時もなお、細やかに自分の感情を描写し続け、同じ症状を持つ大切な人たちのそばにいる方々にも理解を深められるものです。
また、私は今まで全く接点がなかった精神科や隔離病棟のリアル、医療現場についての描写も細かいので、全く知ることのなかったことを、知ることができました。
残念ながら、著者は若くしてこの世を去ってしまいました。
誰にでも大なり小なりの心の傷はあるかと思います。
自分の心と向き合うことが、こんなに苦しいことなんだと改めて理解できたし、親の在り方が子供の心に及ぼす影響についても痛感しました。
これまでの私の言葉の表現では、著者の魂の叫びのように綴られた言葉が詰まったこの本の存在意義が、ほとんど伝わっていないかもしれません。
ただ、誰かに届いてほしい。この本が必要な方に。
最近のコメント